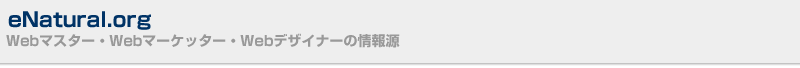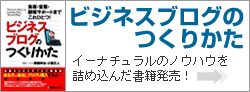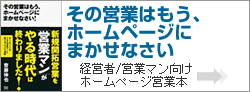2004年11月29日
Yahoo!の検索ビジネス戦略を探る
Yahoo!の検索ビジネス戦略を探る 第1回:Yahoo!検索の現在・過去・そして今後
一番大事なのは、ユーザーが求める情報をいかに簡単に、効率よく得られるかということです。そのために、検索できる範囲を指定できるようにするとか、先ほど触れたように、ユーザーが求めているものが明らかなら直接その情報ページを表示するとか、いろいろな工夫を考えています。ローカルファイル検索はあくまでそうした方法の1つであって、それ1つでユーザーが便利になるというわけではないでしょう。また、ロボット検索だけではなく、ディレクトリも常にフィードバックを踏まえて改善していかなくてはならないし、やれることはまだまだあると思います。
ゴメス、今年秋期の人材派遣サイトランキングを発表
総合1位となったオー人事ネットは、地域や職種、就労期間、オフィス環境などの項目を指定して求人情報を検索でき、サイト全体がわかりやすいナビゲーションでまとめられているほか、派遣登録会の予約システムでは、会場ごとに定員の空き状況が分かるスケジュール表を用意し、電話で問い合わせることなく都合の良い時間帯を予約できる点が便利であると、同社は評価している。
オー人事ネットは、
・機能性と使いやすさ 2位
・安定性と信頼感 1位
・情報量とコンテンツ -
・サービスのきめこまかさ 2位
となっています。ちなみに、1位のオー人事ネットは7.09、2位のリクルートスタッフィングは7.01でそれ程大きな差はありません。逆に、リクルートスタッフィングは、
・機能性と使いやすさ 3位
・安定性と信頼感 2位
・情報量とコンテンツ 2位
・サービスのきめこまかさ 3位
と平均して上位にいます。
企業ユーザーにもブレイクするか?「ビジネスブログ」
個人ユーザーの間で日記や情報発信などのツールとして急速に広まりつつあるブログを、法人向けにビジネスブログとして活用しようという動きが強まっている。ブログ構築ソフトの元祖ともいえる「Movable Type」を開発した米Six apartの日本法人シックス・アパートは、Movable Typeの法人向けパッケージをソフトバンクBB経由で年内に出荷すると10月に発表した。またブログを利用した社外向けWebサイトや社内コミュニケーションツールの構築サービスの提供が各社からアナウンスされている。
BOXERBLOGの方によると「問い合わせは社外向けより社内向けシステムの方が多い」そうです。事件は会議室ではなく現場で起こっていそうですね。
その点ブログは個人が主体となっており、掲示板における話の流れやメールにおける返信の必要性を意識することもないため、どのような情報でも書き込みやすい。また書き込んだ情報はXML形式でデータベースに蓄積されるため、後で検索して容易に取り出すことができる。
社外向けのFAQツールとしてブログが利用できるならば、社内向けのFAQとしても活用できるのは自然の流れでしょう。
しかし、シックスアパートの関氏が「ブログの導入において難しいのは、システムの導入ではなくブログを書いてもらうこと」と話すように、課題はやはりそこですね。その対策としては「ブログを日報形式にして義務化すること」だそうです。
さらに、All About Japanにビジネスブログ関連の記事がありましたので、そちらのリンクも。
私は、自社サイトにブログを活用する大きなメリットのひとつは、「情報整理」と「サイト構成の把握」にもあると思っています。ブログは基本的に時系列で情報が蓄積されていきますが、それぞれの記事に任意に設定したカテゴリーを関連付けることが出来ます。
特に「広報のために」という使い方をしていなくても、これが広報的な役割を果たしています。企業トップの言葉ですから、必然的にそうなりますよね。毎日は無理にしても、些細なことでも頻繁に更新されていると、その会社の印象は良くなるものです。
前ページのように特別なキャンペーンや特定の商品に対して行うだけでなく、例えば自社サイトの一部をブログで構築する場合を想定してみましょう。商品やサービスのページにトラックバックやコメントを受け付けることで、ユーザーの声を集める機会がより多くなり、横の繋がりができ、よりアクセスも集めやすくなります。別段「マーケティング」と構えるまでもなく、一部を「ブログ化」することで、結果的にマーケティング的なメリットがあるのです。
既存客だけのクローズドな利用ではなく、顧客サポートページをオープンにし、情報を共有することで、潜在顧客も含めたより広い層がFAQとして参照することも可能になります。オープンにすることで、しっかりとしたサポートを行っている事が潜在顧客に伝われば、信頼性の向上に繋がりますし、クレームが来たとしても、それに正面から対応する真摯な姿勢を示すことができれば、逆に見ている人の共感を呼ぶ場合もあります。実際に、某大手企業のトップがサービスの不具合に対する謝罪をブログで行ったところ、非常に好意的なレスポンスが返ってきたという事例も耳にします。
サイト検索されやすいキーワードの選び方
ここがコツ インターネットで顧客をつかむ 第6回~サイト検索されやすいキーワードの選び方
Webに掲載するキーワード選びの際に最も重要なのは、「誰にサイトを見つけ出して欲しいのか」、そして「その人はどんなキーワードで検索するのか」といった相手側の視点で考えることです。そんなの当たり前と思われるかもしれませんが、ちょっと気を抜くとWebマスターをはじめとするサイトの持ち主側の視点になってしまいがちです。
何事も顧客の視点に立つというのは大切なことなんですが、確かに言われる通り、視点はずれがちです。そういう場合には、ここでも紹介されている通り、
・Overture キーワードアドバイスツール
・Google アドワーズ広告 キーワードツール
が役に立ちます。
これらのツールは、過去の統計情報から検索されやすいものを表示してくれるので、信頼性が高く、非常に重宝します。ただし過信は禁物です。あまり検索されないけれど、高い確率で次のアクションに至る「キラーキーワード」が抜け落ちてしまいがちなのです。
併せてアクセス解析もきちんとしておきましょう。
2004年11月25日
ネット広告測定の国際ガイドライン設定
ガイドラインでは広告インプレッションの測定方法を具体的に規定。サーバサイドではなくクライアントサイドで広告インプレッションをカウントすること、スパイダーやロボットによる巡回を除くことなどを定め、パブリッシャーや広告配信技術を通じて一貫したやり方で、オンライン広告の正確な測定を目指している。これによって広告主やパブリッシャーにとっての広告売買プロセスを簡素化し、インターネット広告出費を加速させるのが狙い。
2004年11月24日
企業広報担当者、ニュースサイトやメルマガを既存メディアと同等評価
企業広報担当者、ニュースサイトやメルマガを既存メディアと同等評価
ニュースサイトやメールマガジンについては、「新聞・雑誌、電波メディアなど既存メディアと同等に評価している」と答えた企業が過半数となり、これらの企業属性は広く散っているという。一方で既存メディアを重視しているのは、上場企業や、広報部門が社長直轄の企業で占められた。「既存のメディア以上に重視」と回答した企業は8社で、内訳はIT企業に加え、サービス業、小売業、運輸・通信業が1社ずつ。また、「今後、もっと重要になる」と考えているのは建設業だった。
これは興味深い結果ですね。インターネットを活用したプロモーションは中小企業にこそ実施して欲しいな、と思っているのですが。
Webサイト閲覧について、アクセスログをとっているのは、「実施予定」の4社を含めて97社中30社だったそうで、単純にアクセス解析すらしていないとなると、ウェブをマーケティングツールとして活用する、というのもまだまだ難しいのかもしれません。
2004年11月19日
SNS + Blogコミュニティ「B食倶楽部」
書き手はSNS方式で集めるBlogコミュニティ「B食倶楽部」
メイプルはこのほど、食の話題に特化したBlogコミュニティサイト「B食倶楽部」をオープンした。BlogはNTTデータの「Doblog」システムを採用し、書き手として参加するには正体が必要なソーシャルネットワーク(SNS)の仕組みを取り入れた。
ある特定の話題に沿ったblogがぶら下がっているコミュニティサイトは、もしかして初めてでしょうか? ありそうでなかったサービスですね。「B食倶楽部」で注目したいのは、会員になるための条件として既存会員からの紹介、つまりはSNSの形式を取り入れている点です。
コミュニティがその方向性を失わないためには、いかにして「質の高い」会員を獲得するかが大きな命題だと思いますが、SNS形式での会員募集はひとつの解答といえるのではないでしょうか。
スタイルシートでレイアウト
スタイルシートだけで段組を作るという記事より。
スタイルシートには、直接「段組を作る」ために用意された仕組みはありません。しかし、あるプロパティを使うことで、簡単に段組を実現できます。
テーブルレイアウトは、直感的に利用することができ、ある意味では革命的でもありました。しかし、本来の使われ方ではなく、今後はスタイルシートでレイアウトすることが推奨されています。テーブルタグは、あくまでも表組みのためのもの、ということですね。
ぼく自身がそうでしたが、スタイルシートは最初はとっつきにくく、なぜテーブルで表現できるものを別の方法で定義するのか、といった疑問も確かに感じました。が、メンテナンス性や検索エンジン、見る人のことを考えると、スタイルシートでレイアウトした方が良いということが理解できました。
ということで、この記事では非常に分かりやすくスタイルシートによるレイアウト方法がまとめられていますので、もう始めないといけないな、と思っていた人には非常に役立つのではないかと思います。
スタイルシートの段組のメリットも併せて読むと良いかと思われます。
Webマーケティングの近未来 第14回~欧米での企業ブログの現状(その7)
Webマーケティングの近未来 第14回~欧米での企業ブログの現状(その7)
いずれにせよ、ジャーナリストをプロとアマチュアの2つの層として定義して、それぞれへのアプローチを考えるという戦略が、これから確立していくのだと思います。そして、後者もメディアとして、大きな影響力があるという前提でメディア戦略を考えなければなりません。
昨夜、Webマーケティングの近未来シリーズを執筆されている織田さんとお食事する機会に恵まれました。他にもブロガーにお会いしたのですが、みなさんブログから受ける印象とご本人は随分と違いました。ブログの面白さを改めて感じた夜です。
さて、この記事では「PR担当としてブロガーと対応するにはどうすべきか」ということがインタビューされています。検索エンジンで上位表示されたり、口コミで情報が伝播していくことを考えると、既に無視することのできないツールであり「私はブログを全然読まないし、なぜブログが重要なのかわからない」とったことは言っていられない時代に既に突入していると思います。だとすれば、ブログが分かるPR担当も拡充すべきでしょう。
ブロガーへの対応が以下のように。
1)他の行動を起こす前に、まずはブログ界で何を言われているかをよく聞く。PubSub、Technorati、Feedsterは優れたツールです。それらを使って、自社のことについてブログ界で何か語られているか、誰が影響力を持っているか、誰と誰がリンクされているか、を調べます。
2)次は、その中の影響力のあるブロガーたちへ連絡を取ります。あるいはコメントをブログに書きます。このブロガー達と知り合いになりましょう。彼らはジャーナリストではありません。決して、彼らを影響力を使うための手段として扱わないことです。この人たちのことを本当にひとりの人間として気にかけるべきだと思います。プレスリリースなどは送らないこと。必要だと思えば、CEOと直接話をさせるなど、企業の語り口ではなく、個人としてつながれる方法を考えましょう。
3)最後のステップは、このブロガーとの関係を確立した上で、ブログをスタートします。ただし、企業の看板をかぶったブログではなく、社員によるブログです。ここでも、企業の語り口はブロガーに対して通じません。個人が通じるのです。
(1)に関して言えば、日本であれば、
FeedBack - Yet Another RSS Search
Bulkfeeds: Home - RSS Directory & Search
などを利用することができるでしょう。
(2)については、まだ目に見える形では事例は多くありませんが、密かに動いているのではないかと推測されます。実際に、ぼくの個人ブログにもアプローチがありました。それは、新製品を送るので感想を聞かせて欲しい、というメールでした。ブログで書く必要は特にないし、いろいろなネタを扱っている観点から感想を聞かせて欲しい、という主旨でした。もちろん面白ければネタとして取り上げさせて頂く可能性はありますから、実際に影響力のある(信頼感がある or アクセス数がある)複数のブログに掲載されれば、プロモーション効果が期待できるのではないかと思います。
実際のところ、アメリカでの状況がまだまだのようですので、日本でブロガーを巻き込んだPR手法が使われ始めるのは早くても来年早々、遅くても春には始まるのではないかと思います。
ただし、いかにも宣伝的であったり、無差別に商品を送りつけたりすれば、あっという間に悪い立場に立たされてしまうのは言うまでもないでしょう。そういう意味でも、フログの分かるPR担当の重要性は非常に高いと思います。
ビズブロ界のキーマンに聞く!:第1回 TIIDA BLOG
ビジネスブログにて、ビズブロ界のキーマンに聞く!:第1回 TIIDA BLOGを公開いたしました。
ビジネスの、ビジネスによる、ビジネスのための企業blogをピックアップ。いったい、どういうアプローチでblogをビジネスに活用しているのか? blogを運営することでビジネスにどのような影響を与えているのか? キーマンへのインタビューを通じて、ビジネスblog運営の極意に迫ります。
ぼくも同席させて頂いていたのですが、他に例を見ない試みということで、ご苦労もあったかと思いますが、それよりも“楽しい”という気持ちも非常に伝わってきたインタビューでした。
トラックバックなどでリアルに効果が見える良さもありますし、今後はアクセス解析による効果測定などもさらに重要になるな、と写真を撮りながら思ったり。
ご協力頂いた日産の工藤さん、山本さん、ありがとうございました!
2004年11月18日
ビジネスブログ効果?
今日、某出版社からビジネスブログに関する取材を受けました。その中で分かったのですが、ビジネスブログで見た、ということで、意外に取材を受けているblog運営者の方が多いようです。確かに取材する側からすると、ビジネスブログで事例を見てそこから、というのは便利なのかもしれません。もちろん、ビジネスブログ自体も取材はお待ちしています(笑)
2004年11月15日
創業91年、老舗のECも受賞――オンラインショッピング大賞
OLS大賞は、国内ECの育成・発展を目的として1997年にスタートした。ECサイト運営企業などから公募し、エンドユーザーの視点から同委員会などが評価、中小規模のサイトを中心に受賞を決める。
グランプリはマガシークだそうです。「その年のテーマに最もふさわしいサイトに与えられる第2回三石玲子賞」には青空文庫が選ばれています。
グランプリを受賞した「マガシーク」は、女性向けファッション雑誌に掲載された商品を、PCや携帯電話から購入できるサイト。2000年に伊藤忠商事の社内ベンチャーとして発足した同サイトだが「当時は、試着ができない服屋など売れるはずがないと言われていた」(伊藤忠からスピンアウトしたマガシークの井上直也社長)。
それが今は年間20億円を売り上げるサイトに成長しているそうです。
Webマーケティングの近未来 第13回~欧米での企業ブログの現状(その6)
Webマーケティングの近未来 第13回~欧米での企業ブログの現状(その6)
つまり、いきなりここに「社員の情熱を伝えるメディア」が登場したことになり、PRのやり方が大きく変わっています。「人間化した企業の時代(Era of Humanized Business)」がやってきたと言えるでしょう。
「社員の情熱を伝えるメディア」という表現は分かりやすいですね。下記のような事例が取り上げられています。
例えば、マイクロソフトは大きな会社ですが、次世代のIEチームのブログを読むことができ、彼らが製品のことを気にしながら、あるいはユーザーのことを気にしながら、IEを作っている様子が良くわかります。彼らの製品やテクノロジーに対する情熱が伝わってきます。
確かにブログは、書くこと自体にかなりの熱を必要としますから、そういう意味では「情熱を伝える」には最適なメディアと言えるでしょう。気持ちがこもっているかどうか、というのは文章ですぐに分かってしまいますからね。
2004年11月11日
マイクロソフトの検索サービスがスタート
WSJ-マイクロソフト、11日にインターネット検索サービス開始
ニューヨーク(ウォール・ストリート・ジャーナル)米マイクロソフト(Nasdaq:MSFT)は、念願だったインターネット検索サービスを11日に開始する。この事業で最大手のグーグル(Nasdaq:GOOG)にとって、新たな対抗馬が登場することになる。
満を持してという表現が正しいでしょうか? 知名度こそいまいちですが、MSNのアクセス数には目を見張るものがあるので、検索エンジン業界の今後の勢力図に大きな影響を与えることは間違いないでしょうね。
Blogの文字列を視覚化する「BLOG Mater」
Blogから文字列抽出してグラフ化する「BLOG Meter」開始
BLOG Meterは、指定された文字列形式でBlog中に書かれると、BLOG Meter計測エンジンが記録データを抽出し、データとして日々記録していくもの。配布される計測結果表示用URLをWebページやBlogに貼り付することで、グラフ表示される仕組み。
ダイエットや運動の記録としてBlogを利用している人は相当数いると思いますが、そういった方にとっては待ち望まれていたサービスでは。アイディアしだいで、さまざまな展開が出来そう感じがします。
2004年11月 9日
ケイズシステム、MovableTypeが標準装備されたホスティングサービス
ケイズシステム、MovableTypeが標準装備されたホスティングサービス
今回は、初心者にはインストールが難しいとされるMovableTypeをサーバーにプリインストールした状態で提供する。シックス・アパートはMovableTypeのASP版ともいえるTypePadによるblogサービスも行っている。MovableType採用にあたってケイズシステムは、「TypePadの方が確かに操作は簡単です。しかし、カスタマイズするにあたって、MovableTypeの方が汎用性が高く、できることの幅も広いので、企業がwebを制作するにはそちらの方が最適だと思い導入しました」と述べた。
確かにMovable Typeのインストールは一つの、そして大きなハードルです。今後はこうしたサーバも増えてくるかもしれませんね。
ディスク容量は500MB。メールは10アドレスまで設定可能(それ以上は10アドレス毎に月額525円)。有償ライセンス1ユーザー(それ以上は1ユーザー毎に月額525円)、独自ドメイン(com/net/org/info/biz/jp/co.jp)、ウィルス除去サービス、サイト内検索機能、記事投稿スケジュール機能など標準装備。FTPアカウントも発行されるので、カスタマイズも容易に行うことができる。
週刊アスキーでビジネスブログが紹介されました
週刊アスキー 2004/11/23日号の「新着WEBサイト」コーナーで、ビジネスブログが紹介されました。10/21の正式オープンから2週間たらずしかたっていませんが、非常に多くの媒体でご紹介いただいて、企業blogヘの関心の高さを改めて実感しております。
登録サイトも、引き続き募集しております。コチラからどうぞ。
2004年11月 8日
携帯電話にも検索連動型広告
これにより、サーチテリアは、ユーザーがサイト内で検索した内容に適合した広告を配信する検索連動型広告サービスを、まぐまぐが運営する携帯電話向けメールマガジン情報サイト「ミニまぐ」および携帯電話向けメールマガジンに対し提供し、広告を配信していく予定だ。
DoubleClick、売却も含めて今後の選択肢を検討
同社は先週、増収増益の第3四半期(7~9月期)決算を発表したが、その際、Abacus部門とPerformics部門の収益は期待以上だが、Marketing AutomationおよびData Management Solutions事業の収益が予想を下回りそうだとして第4四半期の業績見通しを修正している。
「事業の一部または全面的な売却、資本の再構成、特別配当、株式の買い戻し、またはスピンオフ」も含め、全般的な戦略見直しを検討しているそうです。
2004年11月 5日
7分で分かる10月のBlog界
10月のBlog界は、RSSリーダー、ヤフーの参入、写真や地図との連携を行う新サービス展開など、Blogの多様性を模索する動きなどが幾つも見られた。
10月も色々とありましたね。よく読んでみると、イーナチュラルのビジネスブログについても記載がありました。
Webマーケティングベンダーのイーナチュラルは、10月5日に報じた通り、Webマーケッターのためのビジネスblog情報サイト「ビジネスブログ」を10月21日にオープンした。
11月からはblogをビジネスに活用している会社のインタビュー記事も掲載予定です。お楽しみに。
2004年11月 2日
NS総研、調査レポート「ブログサービスサイト比較調査2004」を発売
NS総研、調査レポート「ブログサービスサイト比較調査2004」を発売
急速に普及が進むブログサービスについて、ユーザ意識・利用動向を調査しました。認知度、認知経路、開始時期、理解度、更新頻度、発信内容など詳細データが掲載されています。
エキサイト、「上場日の社長の一日」をBlogで中継
エキサイトは11月2日、ジャスダック上場日の様子をBlogで中継する。同社代表取締役社長の山村幸広がexciteブログで執筆している「エキサイト社長、山村幸広のインターネットブログ」において、山村氏の様子をリアルタイムに紹介するというもの。
情報を伝える道具としてのblog、アイデア次第で色々と活用できそうです。