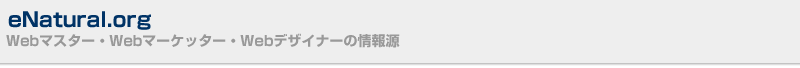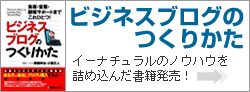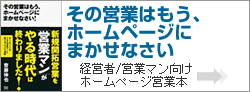2005年3月30日
ウェブログのアイデア!
ウェブログのアイデア!―プロのライター&編集者が教える、ネタの集め方・読ませ方・見せ方のテクニック
・何をするものなのかわからない
・何が面白いのかわからない
・ちょっとかじったけれど、どうしたら面白くなるのかわからない
という人を対象に、いろいろな作り方・使い方・楽しみ方のアイデアを紹介する本です。
弊社のビジネスブログをビジネス向けブログポータルとして紹介して頂きました(226ページ)。
どうやってブログを書いたら良いのか、何を書いたら良いのか、そういったことが分からない人向けのネタ本とも言えると思います。
「アクセス解析でホームページの集客を極める本」に掲載
いま話題になっているアクセス解析の「アクセス解析本」。実はアクセス解析だけに焦点をあてた書籍は、あまり多くはありません。
いちにのアクセス解析も紹介して頂きました(73ページ)。
企業サイトの「使いやすさ」トップは富士通、日経パソコン調査
首位は、2年連続で富士通。2位は日立製作所、3位は日本ヒューレット・パッカード(日本HP)だった。4位には、NTT東日本、日本IBMが入り、上位をIT関連企業が独占した。IT関連企業以外では、サッポロビール、三井住友銀行、三菱商事などが上位に入った。三井住友銀行(昨年の98位から7位に)やJR東日本(同80位から12位に)のように、一気に順位を上げた企業もある。
「使いやすいWebサイトを実現するには、単にWebページのデザインを見直すだけでは駄目だ。企業サイトに求められる要素は、時代とともに変化している。あらゆるユーザーがサービスを利用できるようにするアクセシビリティ対策、検索エンジン利用者への配慮、コンテンツの分かりやすさ、ブランディングなど多岐にわたる。」と記事。
SEO企業による検索ランキング操作の実態
検索ランキングの上下がこれほどまでに大きな意味を持っていることを考えると、ボーザー氏のように検索エンジンに精通した人間が、自分の顧客のランキングをあげるためにあらゆる手を使うのも不思議はでない。また、ボーザー氏自身、悪びれた様子はなく、自分はただ現実に対応しているだけだと主張する。
Googleの検索結果表示に「PageRank」という技術が用いられているのはご存じかと思いますが、「検索エンジンは、非現実的な設定に基づいている。あらゆるリンクを投票とみなしているが、実はそのリンクは売買されているのだ」という指摘。
つまり、リンクには価値があり、一種の“通貨”であると。「PageRank」はGoogleの技術の核となるソフトウェアだが、同時にアキレス腱になっているかもしれない、との指摘も。
グーグル社側は、同社の取る「手法は複雑であり、自動化されているので、人間が結果を操作することはきわめて困難だ」と主張するが、実態はまったく異なる。ボーザー氏によれば、デジタル投票の不正操作は、もはやビジネスの一部と化しているという。
ほとんどこうしたビジネスとGoogleは、いたちごっこになっているんでしょうね。しかし、良くないサービスを利用することで、将来的にペナルティを与えられる恐れがありますので、別のところにお金をかけた方が良いのでは、と思います。
事例として紹介されているSEO企業は、どこも被リンクを獲得するためのサイト群を持っており、現状では外部要因としてのPageRankが重要である、ということも分かります。
2005年3月24日
PPC広告の費用対効果を考える
インターネットで顧客をつかむ 第12回 ~PPC広告の費用対効果を考える
費用対効果を計算する際、まず必要なのは、何をもって「効果があった」とみなすか、ということ。上記の式では「利益」となっていますが、PPC広告の第一目的は集客なのですから、もう少し拡大解釈して、第6回で使ったような、次のアクションにつながるか否か、具体的には、
・サイト運営者の意図通りクリックする
・問い合わせのメールや電話をする
・メールマガジンの購読を登録する
・商品を購入する
といった訪問者の動作をもって効果としたほうがよいでしょう。
「コンバージョン トラッキング」機能や「コンバージョンカウンター」機能が使えない場合の代替として、アクセス解析を使用した方法が紹介されています。
・アクセス解析ソフトの「コンバージョン解析」や「ゴール分析」と呼ばれる機能、もしくはユーザの動きを追跡する機能を使う
せっかく計測するなら厳密に、という気持ちもあるかと思いますが、既存システムが対応していないために、ざっくりしたところから把握していくというのも意外に重要だったりします。
ブログ使い倒し術
小暮がBIGLOBEで連載していた「ブログ使い倒し術」全6回が終了しました。
3ヶ月に渡って連載させて頂いたのですが、短いテキストの中でシンプルに、しかも初心者に向けて書くということで、かなり頭の整理にもなりました。同時に書籍執筆もしていたので、アイデアをブラッシュアップするのにも役立ちました。
基本的なことからブログの事例、メリットなどを簡潔にまとめてありますので、みなさんの参考にして頂けたら幸いです。
「My Yahoo!」にRSSリーダー
ヤフーは3月23日、Yahoo!ID会員向け情報ポータル「My Yahoo!」に、RSSリーダー機能のβ版を追加した。
My Yahoo! のヘビーユーザには待望のRSSリーダ機能が追加されました。モジュールの一つとして追加可能です。
新たに、RSS提供サイトを50件まで登録し、見出しを一覧表示する機能を備えた。各サイトの見出し表示件数は1~10件から選べ、要約も表示できる。
試しに登録してみたところ、今朝更新したデータがあるはずのブログでも昨夜までの分しか表示されませんでした。ということは、Yahoo! がRSSをクロールしてキャッシュしている、ということなんでしょうね。
数に制限があるのでメインでは使えませんが、ホームページをMy Yahoo! にしている人は、よく見るブログをざっくりと新しい情報を眺められて便利かもしれません。
2005年3月23日
ビジネスブログのつくりかた
イーナチュラルの齋藤・小暮が「ビジネスブログのつくりかた」という書籍を執筆しました。ブログ本も世にたくさんありますが、その中からお手にとって頂けたら幸いです。
ブログのビジネス活用に主眼を置き、集客・営業ツールとしてブログを活用するための基礎知識、業種毎の事例、ノウハウなどを解説をしています。
【本の内容】 ブログについて、「聞いたことはあるけど、単なる日記ツールでしょ」なんて思っている方、ハッキリ言ってそれは大いなる誤解です。ブログは構築や運営が簡単で、訪れる人とコミュニケーションを図るためのツールも豊富。それらをうまく利用すれば、あなたの会社の集客・営業・顧客サポートを一手に引き受けてくれる強力な道具になりうるのです。あなたの情報を積極的に発信することによって、お客様とこれまでにない親密なコミュニケーションが実現できるでしょう。こんなにすぐれた情報発信・受信ツールであるブログは、ビジネスの現場でこそ、その真価を発揮します。本書を読んで、ビジネスブログの世界への大きな一歩を踏み出してください!
2005年3月15日
モバイル広告の効果を測定するASPサービス
モバイル広告の「クリック数」「サブミット単価」「掲載媒体」「出稿期間」などの出稿効果をリアルタイムに測定できる。オーリックシステムズと技術提携し、同社のWeb解析アプリケーション「RTMetrics」の基礎技術である“パケットキャプチャ”方式を利用している。
携帯電話の効果測定はどのようにするのかと思っていたのですが、パケットをそのまま調べてしまうのですね。なるほど。
サーチ全盛時代のメディア企業戦略
ライブドアとニッポン放送の報道が連日メディアを埋め尽くしている。ファイナンス、M&A、堀江社長のキャラクターに強く焦点が当たっているが、個人的にはメディアビジネスがどのように変化していくかの先行ケースのひとつとして見ている。
渡辺聡氏の「情報化社会の航海図」より。
比べているのは米国でNew York TimesがAbout.comを買収し、Washington PostがSlateをMicrosoftから買収しているなど古参のメディア企業がインターネット企業を買っている動きである。
堀江社長が口にする「メディアがインターネットを飲み込まないとダメなんですよ」というのは、まさにアメリカで起きつつあるこうした動きのことで、日本ではインターネット企業がメディアを買収しようと試みている訳です。似たような動きとしては、アメリカではAOLがTime Warnerを買収しましたが、それ自体は成功とは言えませんでした。ですので、ライブドアがどのような相乗効果を生むことができるかは非常に興味のあるところです。
そして、アメリカで起こっている「古参のメディア企業がインターネット企業を買っている動き」というのも、いずれ日本に“輸入”されるのではないかと思っています。
New York TimesがAbout.comを買収した意図を、Searchblogから次のように引用しています。
ウェブ上でサーチの存在感が増したことによるユーザー導線の変化と「the long tail」の言葉にまとめられつつある収益ポイントの変化に対応するためだと。インターネット上でメディアビジネスを展開するにあたり、彼らが勝ちパターンに必要と考えたのがAboutを獲得することであった。
最近、「long tail」というキーワードが新たなキーワードとして認知されつつありますが、それを踏まえた上での買収であった、と。
About.comはサーチエンジン広告からの収入が最大化されるようにサイトの作り変えを行ってきていた。いわゆるSEOである。結果、通常15%弱のクリック率が20%まで向上した。
サーチからのトラフィックを上手く活用し、如何に収益に結びつけるかはコマースサイトではもはや常識と言えるが、メディアサイトでも重要度は増している。New York Timesが欲したのは、このノウハウとなる。
例えば弊社でもSEOのノウハウを蓄積しています。さらに、Movable Typeを活用したブログサイト運営に関するノウハウも持っています。と考えると、もしかすると新聞社や出版社から買収を打診される可能性も否定できないのかもしれません。全くの畑違いですが、オールドメディアとニューメディアが融合し、新しいメディアに生まれ変わっていく途中の過程としては当たり前なのかもしれません。
既にキーのひとつとなるコンテンツ、一次情報と品質の良いコラム記事群は保有している。同時に、広告媒体として優れたブランドもある。tailとheadのうち、headは保有している。あとは、tail=aboutと外から得られたトラフィックを上手く捌くサイトの作りを手に入れれば良い。
良いコンテンツを書けるブロガーがいれば、毎月数十万PVのサイトを立ち上げるのも、そう難しくない時代ですから、いくつもの「long tail」を束ねてビジネスにすることも、日本でも十分にあり得る時代になりつつあるのではないでしょうか。
2月のオンラインバンクランキング、1位は?
調査会社のゴメスは14日、「2005年2月オンラインバンクランキング」を発表した。オンライン専業サイトおよびオンライン専業支店サイトのサービスを調査・分析したもので、総合1位がソニー銀行、2位がイーバンク銀行、3位がUFJ銀行インターネット支店となっている。
通帳を不発行にできること、全国から口座開設申込ができること、振込機能を備えていることなどの条件を備えたオンラインバンク8サイトが対象だったそうです。
総合1位を獲得したソニー銀行は、「情報量とコンテンツ」のカテゴリー別ランキングで1位、「総費用」と「安定性と信頼感」で2位とそれぞれ上位に入っているが、「サービスのきめこまかさ」では6位、「機能性と使いやすさ」では5位に止まっている。一方、総合2位のイーバンク銀行は、「総費用」で1位を獲得。3位のUFJ銀行インターネット支店は、「機能性・使いやすさ」で1位となった。
確かに、ソニー銀行はFlashをフル活用したインターフェースなので、最初は慣れが必要かもしれません。そういう意味で、「機能性と使いやすさ」の評価が低いのかも。
海外旅行サイトの比較調査~利用者トップは?
NS総研、海外旅行サイトの比較調査~利用者トップはYahoo!トラベル
ネットアンドセキュリティ総研は10日、海外旅行の予約・決済ができる海外旅行関連サイトの比較調査の結果を発表した。サイトの認知率、訪問率、定期訪問率でYahoo!トラベルがトップを占める結果となった。
「調査は、過去1年間に海外旅行を経験した人で、海外旅行関連サイトを利用した1,123人と利用しなかった342人に対して行なったもの」で、調査対象は、Yahoo!トラベル、MSNトラベル、楽天トラベル、H.I.S、JTB、JAL、Arukikata.comなど20サイトです。
Yahoo! トラベルの認知率は89.7%、定期訪問率が37.5%で、いずれもトップだったそうです。個人的には利用したことがないですし、ほとんどアクセスする機会もなかったので、正直なところでは驚きがありました。
海外旅行関連サイトの認知率では、Yahoo!トラベルが89.7%で最も高く、以下はJTBの80.6%、H.I.Sの79.8%と続く。訪問率では、トップがYahoo!トラベルで74.1%、2位がH.I.Sで64.5%、3位がJALの59.8%となっているほか、定期訪問率ではYahoo!トラベルの37.5%がトップで、以下はH.I.Sの30.5%、JALの28.7%という結果になった。
なぜ旅行サイトを利用しないかと言えば、
「オフラインの店舗にて相談したい」
「紙のカタログのほうが比較しやすく、わかりやすい」
という理由に全く持って同意なのでした。
2005年3月10日
「ブログ自体が人格化する風潮が」
「ブログ自体が人格化する風潮が」Movable Typeのビジネス活用セミナー
新野氏はこれを「ブログは運営者がハッキリとしている。よって、ブログ自体に人格があるような、独特の感じ方がネット文化として根付いているのでは」と分析。企業という法人のサイトであるにもかかわらず、内容が面白ければ一般ブロガーからも好感やシンパシーを得やすい……というのが新野氏の考えだ。
「一般ユーザーのブログでヌーベルブログが話題になるとき、『ヌーベルブログさん』と、さん付けで紹介されることが多い」という特徴に気づき、ブログ自体に人格があるかのように感じられるということを、新野氏が語っていたそうです。
ヌーベルブログはグループブログであるが故、というところもあると思いますが、確かにブログ名に「さん付け」するのは興味深いですね。
ちなみに、ぼくも“[N]氏”という風に、ブログの略号で呼ばれる(書かれる)ことがありますが、それ自体も「ブログ=書き手」が非常に深く認識され結びついており、ある意味ではぼくの「人格=ブログ」として認識されている可能性もあるのかも、と思いました。
さらに「PVがすべてではない」という傾向も顕著だという。従来型のWebサイトではサイト来訪者を増やすこと自体がPR効果を示すが、ブログでは「ブロガーの間でどれだけ話題になるか」が勝負になるためで、荒野氏も「一般ブロガーにリンクしてもらいやすい伝播力のある記事を作成することが重要」と話す。
これはブログの効果測定としては面白い着眼点ですね。つまり、トラックバック数が一つの基準になるでしょうか。他にも、feedbackなどRSS専用検索エンジンで追いかけていると記事が見つかりますので、そういったあたりも指標に組み込むのでしょう。マスに対するアプローチではなく、いかに深いコミュニケーションを取れるか、というところですね。
講演の最後のまとめでは、セミナー参加者に「まずはブログのカルチャーを理解することが重要。ブログの導入を検討している企業担当者は、個人的なものでよいので是非ブログを試してほしい」とのメッセージを寄せた。
これは本当にそう思います。
「美味しいカレーショップを始めたいんです」
「美味しいカレーを食べたことがありますか?」
「いいえ、まだありません」
だと、美味しいカレーショップはそう簡単には作れないと思うのです。
▼ウケるブログ―Webで文章を“読ませる”ための100のコツ
2005年3月 9日
クリック詐欺の被害は10億ドル規模に
クリック詐欺の被害は10億ドル規模に--米SESパネルディスカッション
Harrisonは、GoogleとYahooに掲載した自社の検索広告を、ライバル会社が繰り返しクリックしていることを突き止めた。これは、同氏の会社の宣伝費を浪費させ、同時にライバルの表示順位を上げるための策略だった。GoogleとYahooは不正行為に対する補償を掲げているため、同氏は両社に裏付けとなるデータを送って損害の一部を取り戻し、また一方のサービスからはそのライバルを追い出すことができた。
「200時間以上を犯人探しに費やし、売上にも最低10万ドルの損失があった。お金については大半を取り戻せた」ということで、仮に詐欺に遭っていたとしても、突き止めるためにかなりの労力が必要になるようです。
そして医療や金融、法律といった広告料金の高い業界では、Googleなどの広告ネットワークから利益を上げるためだけの目的でつくられた偽サイトが数多く登場している。
AdSenseを不正クリックして収入を得る、という詐欺ですね。
広告主の側にとっては、自社サイトや広告キャンペーンへのトラフィックを定期的に精査し、問題のクリックを見つけだした上で、広告を掲載した検索エンジンに返金を要求することになるため、クリック詐欺はとりわけ大きな頭痛のタネになっている。さらに、広告主のリンクをクリックするようにプログラムされたオンラインのロボット(もしくは「ボット」)は発見が難しいため、この詐欺がいっそう深刻な問題になることも多い。
マーケティングの新たな主役は請求書?
顧客とのコミュニケーションにWebやメールが広く利用されるようになっている。しかしながら、CRMやビジネスインテリジェンス(BI)などのソフトウェアを提供する米Group1 Softwareのジェフ・コーヘン氏は、「インターネットベースのマーケティングで企業は幾つかの問題に直面している」と指摘する。
当たり前と言えば当たり前なのですが、メールの開封率が下がるなどして、ほぼ間違いなく開封される請求書がワンツーワンマーケティングの切り札の1つとして注目されているそうです。
米American Express(AMEX)はかつて、顧客に送付する利用明細書は、小さなメモ書きのようなものだった。レガシーシステムを利用していたため、フォーマットや印刷形式の柔軟性には限界があったという。そこで、同社は、Group1が提供するアプリケーション「DOC1」を導入した。請求書によるワンツーワンマーケティングを実行しようとしたものだ。
「顧客のクレジットカードによる購買履歴に応じて、パーソナライズした広告を利用明細に印刷するようにしたことで、レスポンス率が10倍以上にまで向上した」という凄い数字が。
「long tail」というマーケティング用語
long tailというのは簡単に言えば、多くの小さなニッチ市場がたくさん存在すれば、それは少数の巨大市場を凌駕することになるという考え方である。かつては非主流やアングラ、インディーズ系だった商品が、今ではベストセラーや大ヒット商品と肩を並べるほどのマーケットシェアを持つようになりつつある。
「最近、long tail(長いしっぽ)というマーケティング用語が頻繁に使われるようになってきた」ということで、英語圏のブログ、ネットではその言葉を見ない日はないそうです。近々、日本にも輸入されるでしょう。
「long tail」はインターネットの特性を生かしたマーケティング理論で、次の3つの基本的なコンセプトからなっているそうです。
・マスからニッチへのシフト。
・供給過多経済――要するに商品棚がいつも商品であふれているという状態で何が起きるか。
・数多くの小さなマーケットが集まると、巨大市場に成り得るということ。
「全商品の中のわずか20%の商品が、売上の80%を作り出す」というパレートの法則がありますが、「long tail」はこのパレートの法則を崩しつつあり、売れないはずの80%の製品が売れるようになってきていると。
あるブロガーの言い方に従えば、「われわれはいま、フォード自動車的な大量生産経済の終焉を目の当たりにしつつあるのかもしれない」ということだ。どんな色でも構わない、君の好きな色をゲットすればいいんだよ、ということである。
「long tail」は覚えておいた方が良さそうです。
2005年3月 8日
オーバーチュア、Yahoo!カテゴリ内で検索連動型広告の配信を開始
オーバーチュア、Yahoo!カテゴリ内で検索連動型広告の配信を開始
例えば、Yahoo!カテゴリの中から、「ビジネスと経済>ショッピングとサービス>財務、金融>保険>生命保険」と選択していった最終ページでは、「生命保険」というカテゴリ名に完全一致するスポンサードサーチの結果が表示される。表示箇所はYahoo!登録サイトの上部で、表示件数は最大3件となる。
露出が増えて何より、かな?
2005年3月 7日
LycosがAsk Jeevesの検索採用
Lycosの検索サービス担当ジェネラルマネジャー、アダム・ソロカ氏は発表資料で「Lycosブランドは検索で知られており、当社はLycos.comをトップクラスの検索サイトとして立て直すべく尽力している」と述べている。
Ask Jeevesのアルゴリズム検索技術「Teoma」を採用するそうです。
ヒット中の「ブログ」、ISPに重い負担、収益化も見えず
こうした負担の増大は加速する一方で、収益化の方向性は見えない。現在ブログサービスは原則無料で、別途サービス内容を拡充した有料コースを設けている事業者がほとんどだが、この課金モデルの成果は芳しくない。「どの事業者も有料コースの利用率は1割に満たないはず」(ニフティのソーシャルシステム部の中泉隆部長)という現状だ。
一言ですが、弊社代表齋藤がインタビューで登場しています。
2005年3月 4日
登録フォームのユーザビリティ
1. 入力項目を可能なかぎり減らす
文字を入力したり項目を選択したりすることは、ユーザーにとって非常に面倒な作業です。
2. 何を入力すべきかを迷わせない
何を入力すべきかが分かりにくい入力フィールドや誤解を招く選択肢も、ユーザーにとって大きな障壁となります。
3. エラーへの対処を容易にする
一度生じたエラーからの復活をいかに簡単にするかが、登録フォーム設計の肝であるともいえます。
ビービットさんの解説です。問い合わせフォーム、ショッピングカート、メルマガ登録フォームなどを作る際に、非常に参考になりそうです。本文では、具体的な解説がされていましたので、是非ご確認下さい。
注文してくれそうな人を検索エンジンから連れてきて、
サイト内でも適切なアピールをして買う気にさせているのに、
いざ注文というところで買う気が失せてしまうフォームってありますよね。
けっこう大事な部分なんですよね。勉強になります。
2005年3月 3日
三井不動産、Movable Type利用のBlogマーケティング開始
三井不動産、Movable Type利用のBlogマーケティング開始
三井不動産は、MovableTypeで構築したBlogを利用した「みんなの住まい」(37sumai.com)でマーケティングをスタートした。
サイトにおけるコンテンツ、エッセイ部分がブログで構築されています。
ブログではコメント、トラックバック共に受付が行われていますが、エントリーの最下段には「「ブログコンテンツ」への投稿規約・トラックバックされる際の注意点」という規約が表示されています。規約を承諾することで投稿できる仕組みとなっています。これは今までには見たことがない方法ですね。
ちょっと物々しいかな、とも思ったのですが、既にいくつか投稿も集まっていますし、大きな障壁にはならないのでしょうか。非常に良い取り組みだと思いますので、後はどれだけ継続していけるか、という部分にかかってくるのでしょうね。
「Search Engine Strategies」開幕--検索広告の人気を反映し大盛況
「Search Engine Strategies」開幕--検索広告の人気を反映し大盛況
SESイベントがこれだけの大盛況を博すのは、GoogleやYahoo傘下のOverture Servicesの影響で検索広告に注目が集まっているためだ。収益率が高いことや広告対象を効率的に絞り込めることが、検索広告の人気の理由だ。主催者によると、今年のSESには1500人以上の人が来場する見込みだという。来場者1500人というのは、ドットコムバブル崩壊前の2000年と比べると5倍近くに相当する人数だ。なお、昨年の来場者数は1100人だった。
Search Engine Strategiesは日本でも4月に開催されます。
全部画像で概要が引用できなかったので、詳細は↓でご覧ください。
Search Engine Strategies Conference & Expo 2005 Japan
去年はGoogleが基調講演を行いましたね。あっという間に満席になったのを覚えています。
昨年レポートは↓でどうぞ。
[eN] Search Engine Strategies 2004 Google基調講演レポート
1年なんて、本当にあっという間です。
最悪のブログキャンペーン事例を検証する
Webマーケティングの近未来 第26回~欧米での企業ブログのケーススタディ(その6)
ただ、口コミはいいことも悪いことも同様に、いや、正確には悪いことほど広がりやすい性格を持っている。アメリカやヨーロッパでも、ブログキャンペーンの失敗は数多く見られる。今回は、アメリカのブロガーの間でいつも最悪のブログキャンペーンとして取り上げられる「Raging Cow」のブログキャンペーンの話をしてみたい。アメリカでまだ多くの企業が企業ブログを始めることに不安がある理由の一つがこの事件にある。
お馴染み織田さんの「Webマーケティングの近未来」からです。安い経費、検索エンジンで上位に表示されやすい、などのメリットばかりに注目が集まりがちですが、確かに一方では使い方を間違えればブログでは悪い噂が伝播していくスピードが速いのもまた事実。先日、あるアイドルがテレビで失言した時にも、ブログを情報が駆けめぐっていったことからも分かります。
あるミルク飲料のキャンペーン失敗例が紹介されています。
ブログキャンペーンでは、この牛のキャラクターを中心にしたブログを開設するとともに、影響力のあるティーンブロガー6人を本社に招待し、製品やプロモーショングッズなどが進呈されたという。そして、彼らのブログでこのRaging Cowのことを書くように依頼し、さらに彼らはRaging Cowとは全く関係がないことにするようにと言い渡されたのである。
やらせですね、これは。
「不自然さが、ブログの商業的な使用を嫌うブログ純粋主義者とでも呼べる人たちにより指摘」され「やり方を批判するコメントやトラックバックを大量」に送られたそうです。これもまた当然の成り行きですね。最後はコメントもトラックバックも受付が停止されたそうですが、
それが火種となり、今度はRaging Cowブログが、ブログとしていかにひどいデザインと内容であるかということが話題になったり、始めはサイトの著作者が誰だか分からなかったのが急にDr. Pepper/7upが著作者として出てきた、ということに発展してきた。
どんどん問題は大きくなっていったそうです。
そして同時に、あるSEOマーケティング関係者が自らのブログで、Raging Cowの不買運動を始めた。Raging Cow不買バナーとコードを公開し、他のブロガーにブログに貼り付けるように呼びかけ、その不買運動の進展の様子をブログで追いかけた。バナーが張られる数にしたがって、このサイトは検索エンジンで上位に上がり、最終的には「Raging Cow」を検索すると2位になるまでになった。
まさに「やってはいけない」をやってしまった事例ですね。ブログのことはとりあえずブロガーに聞け、と思うのですが、誰もブロガーに意見は聞かなかったのでしょうか。口コミの良い側面だけを見ていたのでしょうか。「隠し事をせず、消費者と同じ目線で真摯に対応する態度」が求められます。